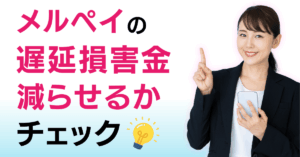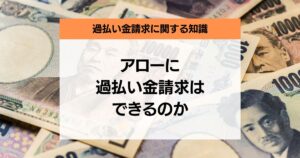借金問題の解決手段として広く知られる「任意整理」ですが、返済が思うように進まず、やむを得ず「自己破産」への切り替えを検討する方も少なくありません。しかし、自己破産という言葉には強い不安や誤解がつきものです。
本記事では、任意整理から自己破産に切り替える理由やタイミング、実際に切り替えた場合に生じる影響、手続きの流れについて詳しく解説します。
知恵袋で話題の任意整理から自己破産にする流れと影響
自己破産へ切り替えるまでの流れ
任意整理から自己破産に移行する場合、まずは現在の任意整理を受任している司法書士・弁護士に「返済が難しいので自己破産にしたい」と相談します。
任意整理はあくまで分割返済の合意なので、支払が続けられないと分かった時点で、早めに手続きを自己破産へ切り替える方が安全です。弁護士が新たに自己破産の受任通知を出すと、債権者からの督促は止まります。
その後、以下の準備を進めます。
- 家計の収支表を2〜3か月分作成
- 給与明細、通帳コピー、借入一覧、クレジット明細などの提出
- 賃貸契約書や車・保険・解約返戻金がある商品の資料も用意
- コロナ後遺症など、働けない状況を証明する診断書があると有利
弁護士がこれらをもとに申立書を作成し、地方裁判所に提出します。申立後、裁判所から呼び出しがあり、1回の審尋に出廷すれば通常は手続きが完了します(同時廃止事件の場合)。管財事件になると、管財人との面談や追加書類の提出が必要になることもあります。
注意すべきポイントと生活への影響
家財道具・日常生活品は原則残せる
テレビ・冷蔵庫など通常の生活に必要なものは処分対象になりません。自動車や20万円以上の資産がある場合は換価対象になる可能性があります。
家賃やルームシェアは基本的に継続可能
賃貸契約者本人が自己破産しても、家賃を払えていれば退去を求められることは通常ありません。ただし、家賃保証会社が連帯保証している場合は再契約を求められることがあります。
携帯・クレカは利用停止・解約の可能性あり
自己破産をすると、信用情報に記録されるため、今後5〜10年はクレカや新規ローンが難しくなります。携帯の分割払いも審査落ちしやすくなります。
費用目安
同時廃止なら弁護士費用は20〜30万円程度が相場。管財事件になると裁判所費用や管財人報酬を含めて50万円以上になることもあります。
今の収入(手取り21万円)で47,000円を払うのが難しくなってきた時点で、早めに自己破産の相談をする方が安全です。特にコロナ後遺症など健康上の理由がある場合は、免責不許可になる可能性は低く、申立に有利な資料になります。
任意整理から自己破産に切り替えるとどうなる
任意整理による返済が半年以上滞ったり、再度の借り入れで借金が増加してしまった場合は、自己破産を検討するタイミングといえます。弁護士や司法書士に相談し、現時点での収支状況と債務総額をもとに、法的整理の選択肢を再確認することが重要です。
借金の免責による経済的な影響がある
自己破産をすると、原則としてすべての借金が免除(免責)されます。これにより経済的な再スタートを切ることができますが、同時に一部の契約(携帯の分割払いやローン契約)も解消されるため、生活の再構築には一定の準備が必要です。
財産や資産へ影響
自己破産では、一定額を超える財産は原則として処分されます。
例えば、価値のある不動産や車、高額な貯金などは差し押さえの対象となります。ただし、日常生活に必要な家具や家電などは、通常、処分の対象にはなりません。
家族や職場への影響はあるか
自己破産は個人の手続きであり、家族に借金の返済義務が及ぶことはありません。
ただし、保証人となっている場合は別です。また、職場に知られることは基本的にありませんが、一部の職業(警備員、保険外交員など)では資格制限が生じる可能性があります。
信用情報への登録とその期間
自己破産を行うと、信用情報機関に「事故情報」として登録され、約5〜10年間はクレジットカードの利用や新たな借り入れが難しくなります。この期間中は、いわゆる「ブラックリスト」状態となり、金融取引に制限がかかります。